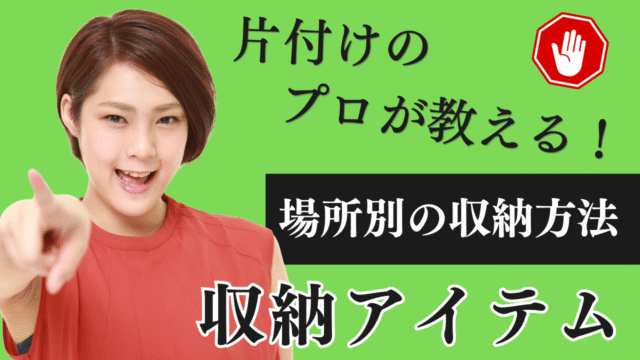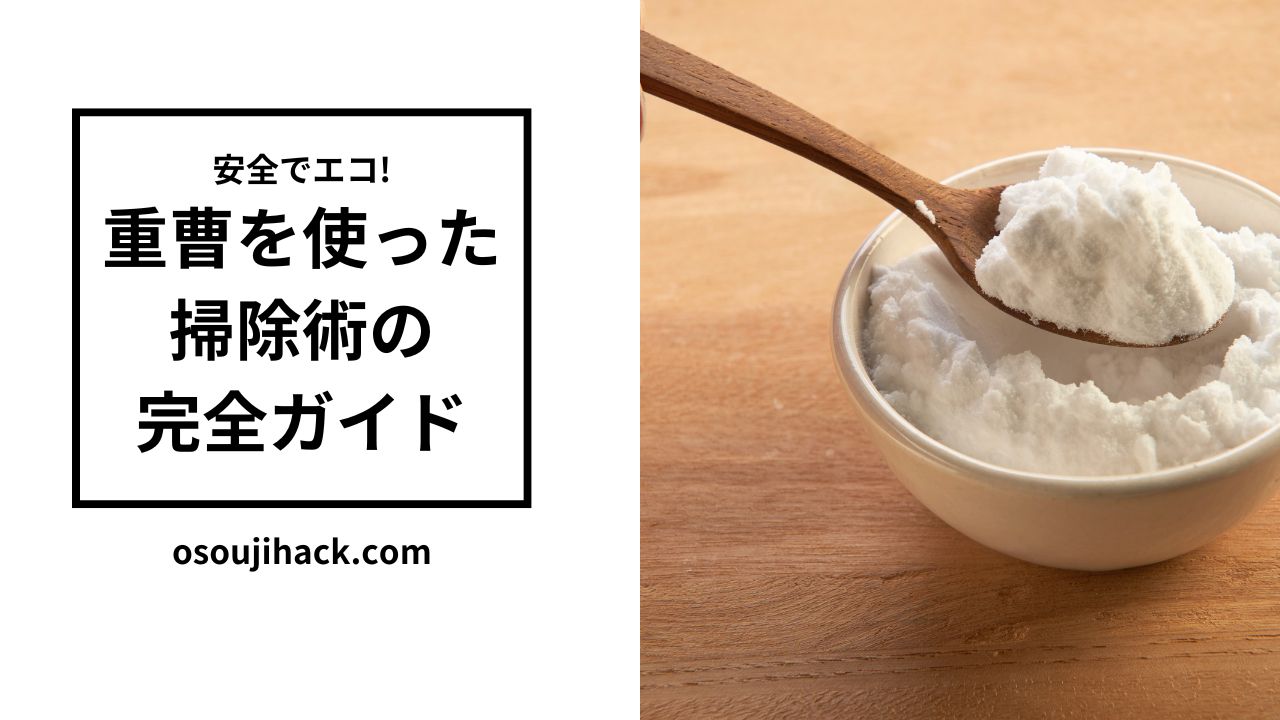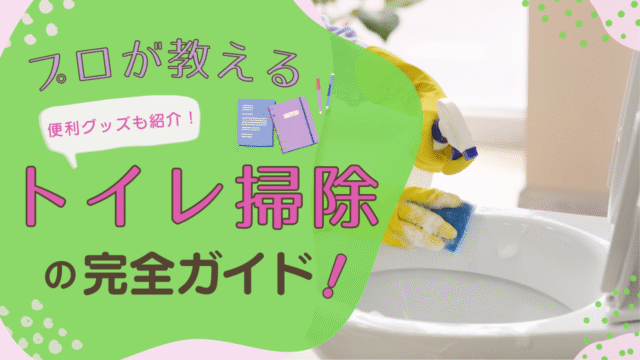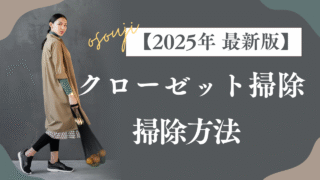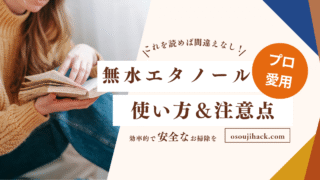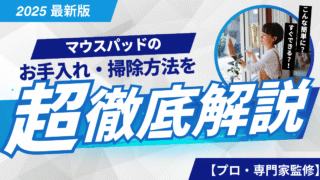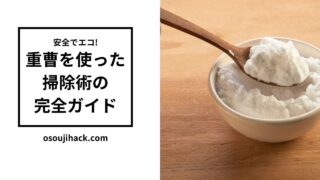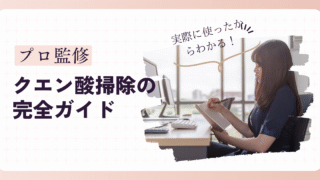※当ページのリンクには広告が含まれています。商品リンクには新品在庫がない場合、中古のものも記載しています。
キッチン、お風呂、リビング…家の中のあちこちに溜まるしつこい汚れ。強力な洗剤を使ってもなかなか落ちないし、手荒れやツンとくる匂いも気になりますよね。そんな悩みをすべて解決してくれるのが、重曹です。
・重曹とは?
・汚れ別の掃除方法が知りたい!
・重曹を使用して掃除する上でおすすめする製品は?
この記事では、なぜ重曹がこれほどまでに万能なのか、そしてどんな汚れにどう使えばよいのかを、科学的なメカニズムから具体的なテクニックまで徹底解説します。環境にも、そして体にも優しい重曹の力を味方につけて、掃除の時間をグッと短縮しましょう。
この記事の監修は

最新の投稿
 お風呂2025年9月14日汚れの原因から落とし方から予防まで、プロが教える風呂掃除の完全ガイド!
お風呂2025年9月14日汚れの原因から落とし方から予防まで、プロが教える風呂掃除の完全ガイド!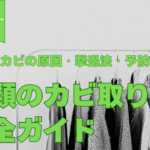 カビ防止2025年9月11日【衣類のカビ取り完全ガイド】恐ろしい衣類のカビ!原因から撃退法、予防策まで徹底解説!
カビ防止2025年9月11日【衣類のカビ取り完全ガイド】恐ろしい衣類のカビ!原因から撃退法、予防策まで徹底解説! 乾燥機2025年9月10日【徹底解説!】乾燥機の嫌な臭いを完全解決する原因別対処法と予防策
乾燥機2025年9月10日【徹底解説!】乾燥機の嫌な臭いを完全解決する原因別対処法と予防策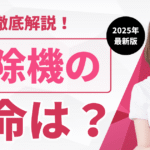 掃除機2025年9月3日【プロ監修】掃除機の寿命ってどれくらいなの?買い替え時期や長持ちさせる方法も記載!
掃除機2025年9月3日【プロ監修】掃除機の寿命ってどれくらいなの?買い替え時期や長持ちさせる方法も記載!
重曹とは?その驚きの洗浄メカニズム
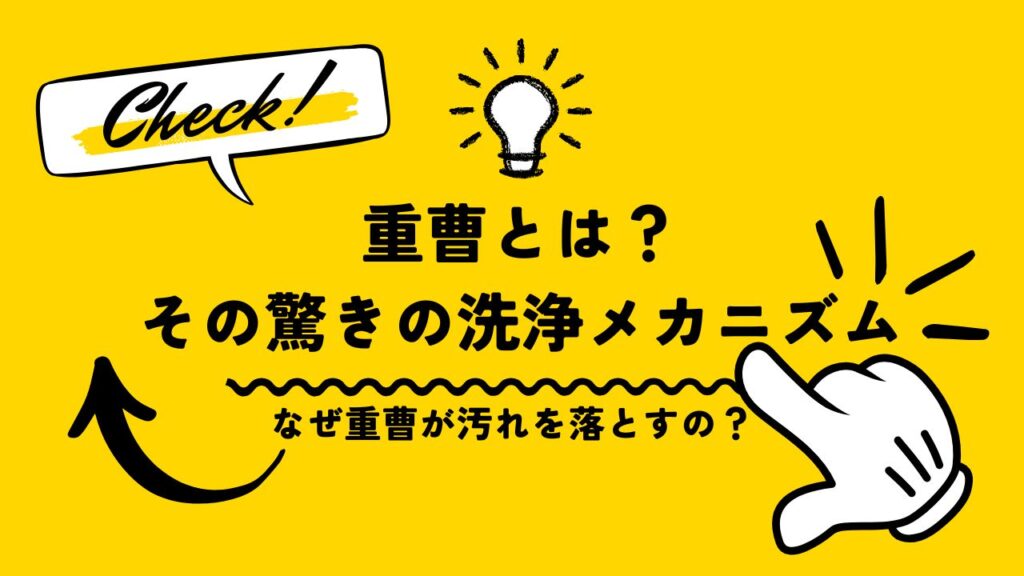
重曹(炭酸水素ナトリウム、ベーキングソーダ)は、弱アルカリ性の性質を持つ白い結晶性の粉末です。この性質が、私たちの生活に潜むさまざまな汚れを効果的に落とす鍵となります。
なぜ重曹が汚れを落とすの?
重曹が汚れを分解するメカニズムは、主に以下の3つの化学的・物理的作用に基づいています。
- 中和作用
私たちの身の回りにある汚れの多くは、酸性です。例えば、料理の油汚れ、皮脂汚れ、手垢、湯垢などは、pHが酸性に傾いています。重曹は弱アルカリ性なので、これらの酸性の汚れと化学反応を起こし、中和して水に溶けやすい状態に変えます。 - 研磨作用
重曹の粒子は、非常に細かく、硬度が低いため、対象物に傷をつけることなく汚れを削り落とすクレンザーのような役割を果たします。特に、シンクやコンロの焦げ付き、茶渋、水垢など、こびりついた汚れを物理的に取り除くのに効果的です。 - 乳化作用
油と水は通常混ざり合いませんが、重曹は界面活性剤のような働きをします。これにより、油を微細な粒子に分解し、水の中に分散させる「乳化」を促します。
汚れ別!重曹を使った徹底掃除テクニック
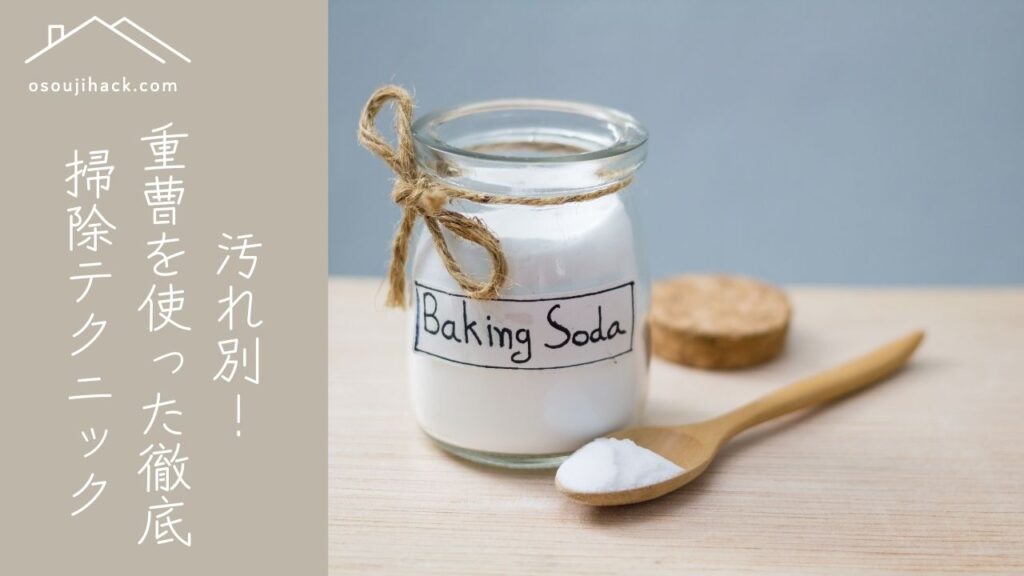
「重曹がなぜ汚れを落とすのか」を理解したところで、次は具体的な汚れに合わせた使い方を見ていきましょう。キッチン、水回り、リビングなど、場所ごとに最適な重曹掃除テクニックを詳しく解説します。
🍳 キッチン周り
【準備するもの】
- 重曹
- ぬるま湯
- スプレーボトル
- スポンジ
- 古歯ブラシ
- マイクロファイバークロス
- ゴム手袋(手荒れ防止のため)
- 新聞紙またはビニールシート(養生用)
1. コンロ(五徳・コンロトップ)の掃除

- 養生する
- 作業スペース(コンロ周り)に新聞紙やビニールシートを敷き、床や壁に汚れが飛び散るのを防ぎます。
- 五徳のつけ置き洗い
- シンクやバケツに、五徳が浸るくらいのぬるま湯(40〜50℃)を張ります。
- ぬるま湯1リットルに対し、重曹大さじ3〜5杯程度を入れ、よく混ぜて溶かします。
- 五徳を入れ、2〜3時間、または一晩つけ置きします。
五徳周りに関してより詳しく記載している記事を下記に記載しましたので興味がある方はぜひお読みください。

熱いお湯を使うと、重曹の洗浄効果がさらに高まります。やけどに注意してください。
- コンロトップの掃除:
- 重曹ペーストを作る
- 重曹に少量の水を少しずつ加え、練り歯磨きくらいの固さになるまで混ぜます。
- ペーストを塗る
- コンロトップの焦げ付きや油汚れがひどい部分に、重曹ペーストを塗り付けます。
- 汚れの程度に合わせて、15分〜30分ほど放置します。
- 擦り洗い
- スポンジ(研磨剤の入っていないもの)を使って、円を描くように優しく擦り洗いをします。
- 五徳のつけ置きも同様に、スポンジや古歯ブラシを使ってこびりついた汚れを落とします。特に溝や網目になっている部分は、古歯ブラシが威力を発揮します。
- 重曹ペーストを作る
- 仕上げ:
- 五徳は、ぬるま湯で重曹をきれいに洗い流します。
- コンロトップは、濡らしたマイクロファイバークロスで重曹を拭き取ります。
- 重曹が残らないように、数回に分けて拭き取ることが大切です。
- 最後に乾いた布で水気を拭き取り、完全に乾燥させます。
2. 換気扇・フィルターの掃除

- 換気扇の部品を外す:
- フィルター、ファン、オイル受けなど、取り外せる部品をすべて外します。
- つけ置き液を作る
- シンクや大きめのバケツに、部品が浸るくらいのぬるま湯を張ります。
- ぬるま湯1リットルに対し、重曹カップ1/2〜1杯程度を入れ、よく溶かします。
- 【ポイント】 換気扇の油汚れはしつこいので、コンロよりも重曹の濃度を濃くするのがコツです。
- つけ置きする
- 外した部品をすべてつけ置き液に浸します。
- 30分〜1時間、または汚れがひどい場合は一晩つけ置きします。
ぬるま湯が冷めてしまうと効果が半減するため、時々お湯を足すか、熱めのお湯で始めると良いでしょう。
- 擦り洗い
- つけ置き後、油汚れが浮き上がってきたら、スポンジや古歯ブラシで擦り洗いします。
- ファンの溝や細かい部分は、古歯ブラシが特に有効です。
- 本体の拭き掃除:
- 重曹スプレーを作る:
- スプレーボトルに、ぬるま湯100mlに対し、重曹小さじ1杯程度を入れてよく混ぜます。
- 拭き掃除:
- 重曹スプレーを換気扇本体の内側や、拭き掃除したい部分に吹き付けます。
- 5〜10分ほど放置し、油汚れを浮かび上がらせます。
- マイクロファイバークロスで丁寧に拭き取ります。
- 重曹スプレーを作る:
- 仕上げ:
- つけ置きした部品は、ぬるま湯で重曹と汚れをきれいに洗い流します。
- 洗った部品は、完全に乾かしてから元の場所に戻します。
これらの手順を参考に、重曹を使ってコンロや換気扇をピカピカにしてみてください。定期的なお手入れをすることで、大掃除の手間がぐっと減ります。
3. 鍋の焦げ付きの掃除

鍋の焦げ付きは、炭化した汚れであり、酸性の油汚れとは少し性質が異なります。重曹の研磨作用と泡の力を活用して、焦げ付きを柔らかくして剥がれやすくするのがポイントです。
- 重曹
- 水
- スポンジ
- 木製のヘラまたは古歯ブラシ
- 水を張る
- 焦げ付いた鍋に、焦げ付き部分が完全に浸るくらいの水を入れます。
- 重曹を入れる
- 鍋に入れた水1リットルに対し、重曹大さじ2〜3杯程度を入れます。
焦げ付きがひどい場合は、重曹の量を少し多めにしても構いません。
- 鍋に入れた水1リットルに対し、重曹大さじ2〜3杯程度を入れます。
- 火にかける
- 弱火〜中火にかけ、沸騰させます。
- 沸騰したら火を止め、そのまま放置します。
重曹と水が沸騰することで、焦げ付きに重曹の成分が浸透し、炭化した汚れを分解し、浮き上がらせる効果が期待できます。
- 放置する
- お湯が完全に冷めるまで、数時間〜一晩放置します。
- 重曹のアルカリ成分と泡の力が、焦げ付きを柔らかくして剥がれやすくしてくれます。
- 焦げ付きを剥がす
- 鍋のお湯を捨てます。
- 柔らかくなった焦げ付きを、木製のヘラや古歯ブラシで優しくこそげ落とします。
- このとき、力を入れすぎると鍋に傷がつく可能性があるため、焦らず丁寧に行うことが大切です。
- 仕上げ:
- 残った焦げ付きや汚れは、重曹ペースト(重曹に少量の水を加えて練ったもの)をスポンジにつけて優しく擦り洗いします。
- 最後によく水で洗い流し、水分を拭き取って完了です。
【焦げ付きがひどい場合の裏技】
- 重曹ペーストでパック:
- 焦げ付きが硬くて落ちない場合は、鍋のお湯を捨てた後、焦げ付き部分に直接重曹ペーストを塗り付け、ラップをかぶせて数時間〜一晩放置します。
- この「重曹パック」は、重曹の成分をじっくり浸透させることで、頑固な焦げ付きも柔らかくしてくれます。
- 重曹+お酢:
- 焦げ付きがひどく、上記のやり方でも落ちない場合は、「重曹」と「お酢」を組み合わせてみてください。
- 焦げ付いた鍋に重曹を大さじ2〜3杯入れ、水を少量入れてペースト状にします。
- その上から、お酢を少量(大さじ1〜2杯)加えると、重曹とお酢が反応して泡立ちます。この泡が焦げ付きを剥がすのを助けます。
- しばらく放置した後、木製のヘラや古歯ブラシでこそげ落とします。
- 【注意】 この方法はステンレス鍋などには有効ですが、アルミ鍋は変色する可能性があるので避けてください。
- 焦げ付きがひどく、上記のやり方でも落ちない場合は、「重曹」と「お酢」を組み合わせてみてください。
これらの方法を試して、大切な鍋をきれいに保ってください。日頃から焦げ付きを予防することも大切です。例えば、料理をする際に焦げ付きやすいものは、かき混ぜながら調理する、火加減に注意する、などが挙げられます。
4. 排水溝のぬめり・消臭

排水溝のぬめりの原因は、石鹸カス、油汚れ、髪の毛、食べ物のカスなどが混ざり合い、雑菌が繁殖することです。これにより、嫌な臭いも発生します。重曹は、これらの汚れを分解する力と、消臭効果を併せ持つため、排水溝の掃除に最適です。
- 重曹
- お酢
- 古歯ブラシ
- ゴム手袋
\重曹の購入はこちらから!/
【手順】
- ゴミを取り除く
- 排水溝のフタ、ゴミ受け、排水トラップ(椀型になっている部品)をすべて外します。
- ゴミ受けに溜まった髪の毛やゴミをしっかりと取り除きます。
- 重曹を振りかける
- 排水溝全体に、重曹をたっぷりとまんべんなく振りかけます。
- ゴミ受けや排水トラップにも、重曹をまんべんなく振りかけます。
- お酢をかける
- 重曹を振りかけた上から、お酢をゆっくりと回しかけます。
- 排水溝の奥の方まで泡が届くように、全体に行き渡らせるようにかけてください。
- 放置する
- 泡が発生している状態で、30分〜1時間ほど放置します。
- この間に、重曹とお酢が汚れを分解し、消臭も同時に行ってくれます。
- 擦り洗い
- 時間が経ったら、ぬめりが取れきれていない部分を古歯ブラシで擦り洗いします。
- 排水トラップやゴミ受けの細かい部分も、古歯ブラシを使うと綺麗になります。
- 仕上げ
- 最後に、40℃〜50℃くらいのぬるま湯で、泡と汚れをすべて洗い流します。
- 全体を洗い流したら、外していた部品を元に戻して完了です。
熱湯をかけると、プラスチック製の部品が変形する可能性があるため、必ずぬるま湯を使用してください。
この方法で、嫌なぬめりや臭いをスッキリ解消し、快適なキッチンや洗面所を保ってください。
💧 水回り
水回りの掃除には、弱アルカリ性の重曹が効果的です。水垢や石鹸カス、ぬめりなどの酸性汚れを中和・分解することで、環境にも人体にも安全に家中をピカピカにできます。
特に、シンクや排水口、お風呂、トイレの掃除において、重曹は強力な洗浄力を発揮します。
5. 浴槽の湯垢・石鹸カス

浴槽の湯垢や石鹸カスは、水道水のミネラル分や皮脂汚れ、石鹸の成分が混ざり合ってできる「酸性」の汚れです。このため、「弱アルカリ性」の重曹が、汚れを中和して分解するのに非常に効果的です。
- 重曹
- スポンジ
- スプレーボトル
- 古歯ブラシ
- マイクロファイバークロス
- 浴槽全体に重曹を振りかける
- 浴槽のぬれた状態のまま、全体にまんべんなく重曹を振りかけます。
- 特に湯垢や石鹸カスが気になる部分には、少し多めに振りかけるのがコツです。
- スポンジで擦り洗い
- 重曹を振りかけた後、スポンジで優しく円を描くように擦り洗いをします。
- 重曹の粒子が、研磨剤の役割を果たし、汚れを削り取ってくれます。力を入れすぎると浴槽に傷がつく可能性があるため、あくまで優しく洗ってください。
- 部分的な汚れの対処
- 重曹ペーストを作る
- 湯垢や石鹸カスが特にこびりついている場合は、重曹に少量の水を加えて練り、歯磨き粉くらいの固さのペーストを作ります。
- ペーストを塗る
- 汚れが気になる部分に重曹ペーストを塗り付け、5分〜10分ほど放置します。
- 溝や蛇口の付け根など、細かい部分は古歯ブラシにペーストをつけて擦ると効果的です。
- 重曹ペーストを作る
- 洗い流す:
- 擦り洗いをした後、シャワーで浴槽全体を重曹が残らないようにきれいに洗い流します。
- 仕上げ
- 最後に、マイクロファイバークロスなどで水気を拭き取ります。
これらの方法を参考に、重曹を使って浴槽を清潔に保ってください。定期的なお掃除で、いつでも快適なバスタイムを楽しめるようになります。
承知いたしました。続いて、鏡や蛇口についた水垢を重曹で落とす方法について、超詳しく解説します。
6. 鏡・蛇口の水垢

鏡や蛇口につく水垢は、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が固まったもので、アルカリ性の汚れです。このため、重曹は直接的な効果が薄い場合があります。そこで、水垢掃除には酸性の力を持つお酢やクエン酸と重曹を組み合わせて使うことが非常に効果的です。
【準備するもの】
- 重曹
- お酢、またはクエン酸
- スプレーボトル
- マイクロファイバークロス
- キッチンペーパー
- 水垢の正体を理解する
- 水垢はアルカリ性の汚れなので、酸性の洗剤がよく効きます。お酢やクエン酸の力で水垢を分解し、重曹で最終的な汚れを落とす、という合わせ技が効果的です。
- クエン酸パックを作る
- クエン酸スプレーを作る
- スプレーボトルに水200mlとクエン酸パウダー小さじ1を入れ、よく振って溶かします。
- パックする
- 鏡や蛇口の水垢が気になる部分に、キッチンペーパーを貼り付けます。
- その上から、作ったクエン酸スプレーをたっぷり吹き付け、全体を湿らせます。
- クエン酸スプレーを作る
- 放置する
- 30分〜1時間ほど放置します。
- 水垢がひどい場合は、数時間〜一晩放置するとさらに効果的です。
- 重曹で磨く
- パックに使ったキッチンペーパーを剥がします。
- 水で濡らしたマイクロファイバークロスに重曹を少量つけ、水垢の部分を優しく擦り磨きします。
- 仕上げ
- 最後に、水で濡らした別のマイクロファイバークロスで重曹をきれいに拭き取ります。
- 乾いたマイクロファイバークロスで水気を拭き取り、乾かすと、ピカピカに仕上がります。
クエン酸で柔らかくなった水垢が、重曹の研磨作用で簡単に落とせます。
🏠 リビング・その他
リビングや寝室は、家族が最も長い時間を過ごす場所です。日々のホコリや手垢、家具の油汚れなど、さまざまな汚れが蓄積します。ここでも重曹は、研磨作用や消臭効果を活かして大活躍します。環境に優しく、小さな子どもやペットがいるご家庭でも安心して使える重曹を使った掃除術で、リビング全体を清潔で心地よい空間に変えましょう。
カーペットの消臭

カーペットに染み付いた嫌な臭いは、皮脂や汗、食べこぼし、ペットの毛などが原因で、雑菌が繁殖することによって発生します。重曹は、これらの臭いの元となる物質を吸着・中和する力を持つため、カーペットの消臭に非常に効果的です。
【準備するもの】
- 重曹
- 掃除機
- 目の細かいザルやふるい
- 古歯ブラシ
- 重曹をカーペットに振りかける
- カーペット全体に重曹をまんべんなく振りかけます。
- 臭いが気になる部分は、少し多めに振りかけます。
- 放置する
- 重曹を振りかけたら、そのまま30分〜1時間、または一晩放置します
- 部分的な汚れの対処:
- カーペットにこぼした飲み物や食べ物のシミがある場合は、放置している間に古歯ブラシに重曹をつけて、軽く擦ります。
- このとき、汚れを広げないように、外側から内側に向かって擦るのがコツです。
- 重曹を吸い取る
- 放置時間が経ったら、掃除機で重曹をすべて吸い取ります。
- 重曹は粒子が細かいため、掃除機のヘッドをゆっくり動かし、隅々まで丁寧に吸い取ることが重要です。重曹が残ると、カーペットが白っぽく見えたり、踏んだときに粉が出たりすることがあります。
【日常的な予防策】
- 定期的な掃除
- カーペットの臭いを防ぐためには、月に1回程度、今回ご紹介した重曹の消臭方法を行うのが効果的です。
- 換気
- 定期的に窓を開けて換気を行い、湿気を取り除くことも、雑菌の繁殖を防ぎ、カーペットの臭いを予防する上で大切です。
この方法で、重曹を使ってカーペットを清潔に保ち、リビングを快適な空間にしてください。
承知いたしました。続いて、靴箱や冷蔵庫で使える重曹の消臭剤について、超詳しく解説します。
8. 靴箱・冷蔵庫の消臭剤

靴箱や冷蔵庫の嫌な臭いは、それぞれ靴に付着した汗や雑菌、食品の臭いなどが原因です。重曹は、これらの臭いの元となる「酸性」の臭いを中和し、吸着する効果に優れているため、天然の消臭剤として非常に役立ちます。
【準備するもの】
- 重曹
- 空き瓶や密閉できる容器
- 通気性の良い布
- 輪ゴム
- 重曹を容器に入れる
- 空き瓶や容器に、重曹を入れます。
- 重曹は湿気を吸着する性質もあるため、容器に入れる重曹の量は、消臭したい場所の広さに合わせて調整してください。
- 容器は、口が広い方が空気と触れる面積が増え、消臭効果が高まります。
- 布でフタをする
- 重曹を入れた容器の口を、通気性の良い布(ガーゼや不織布)で覆い、輪ゴムでしっかりと留めます。
- 重曹がこぼれないように、しっかりと固定してください。
- これにより、重曹が臭いを吸着しやすくなります。
- 設置する
- 靴箱の場合
- 作った重曹消臭剤を、靴箱の中に置くだけでOKです。
- 靴箱の隅や、臭いが気になる場所に設置してください。
- 冷蔵庫の場合
- 重曹消臭剤を、冷蔵庫の棚やドアポケットなど、臭いが気になる場所に設置します。
- 靴箱の場合
- 交換時期
- 重曹の消臭効果は、約2〜3ヶ月で薄れてきます。
- 定期的に重曹を交換し、新しいものに作り直してください。
- 消臭剤として使った後の重曹は、そのまま捨てずに、掃除に再利用できます。
- 例えば、排水溝に流してぬめり取りに使ったり、鍋の焦げ付き洗いに使ったりすることができます。
これらの方法で、重曹を使って靴箱や冷蔵庫の嫌な臭いを手軽に解消し、清潔な状態を保ってください。
賢く使いこなす!重曹の応用テクニックと注意点
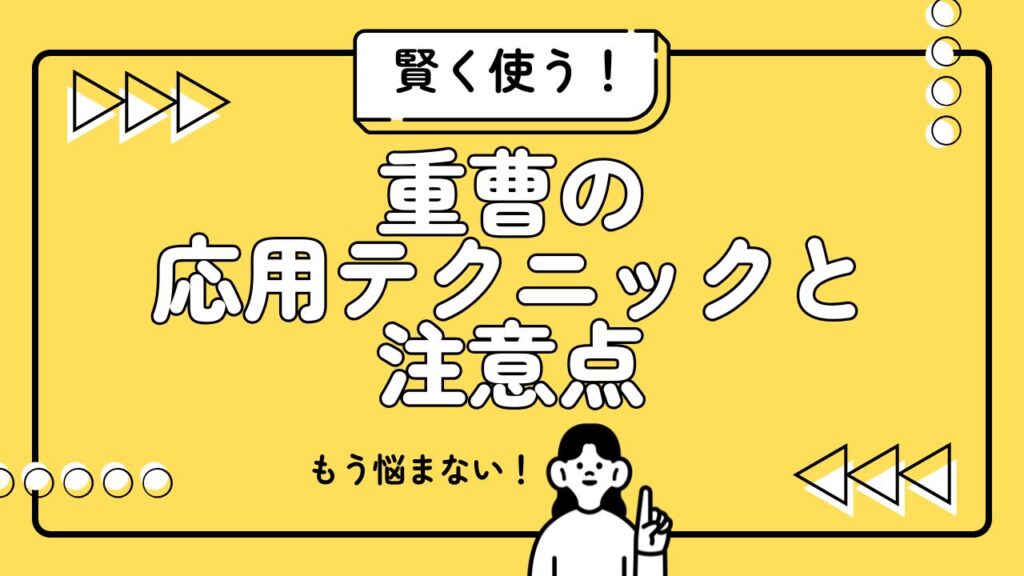
重曹は単体でも十分な効果を発揮しますが、使い方や他のアイテムとの組み合わせ方を知ることで、さらに掃除の幅が広がります。ここでは、重曹を使いこなすための応用テクニックと、安全に使うための注意点をご紹介します。
🌿 重曹水の作り方と活用法
- 基本の重曹水
水200mlに重曹小さじ1~2を溶かします。軽い手垢や皮脂汚れ、電化製品の表面を拭くのに適しています。 - 濃度が高い重曹水
水200mlに重曹大さじ1を溶かします。頑固な油汚れや、より強力な洗浄力を求める場合に活用できます。
🚨 重曹を使う上での注意点
- 使えない素材
アルミニウム製品、漆器、木製品、畳、ニス塗りの家具などは、重曹によって変色や傷みの原因になることがあります。使用前に必ず目立たない場所で試すか、メーカーの注意書きを確認しましょう。 - 手荒れ対策
重曹は弱アルカリ性ですが、肌が弱い方は手荒れを起こすことがあります。ゴム手袋を着用して掃除を行うことをお勧めします。 - 用途ごとの使い分け
重曹には「食用」「掃除用」「工業用」などがあり、純度が異なります。口に入るものには食用、掃除には掃除用のものを使用するなど、用途に合ったものを選びましょう。
掃除のプロがおすすめする重曹はこちら!
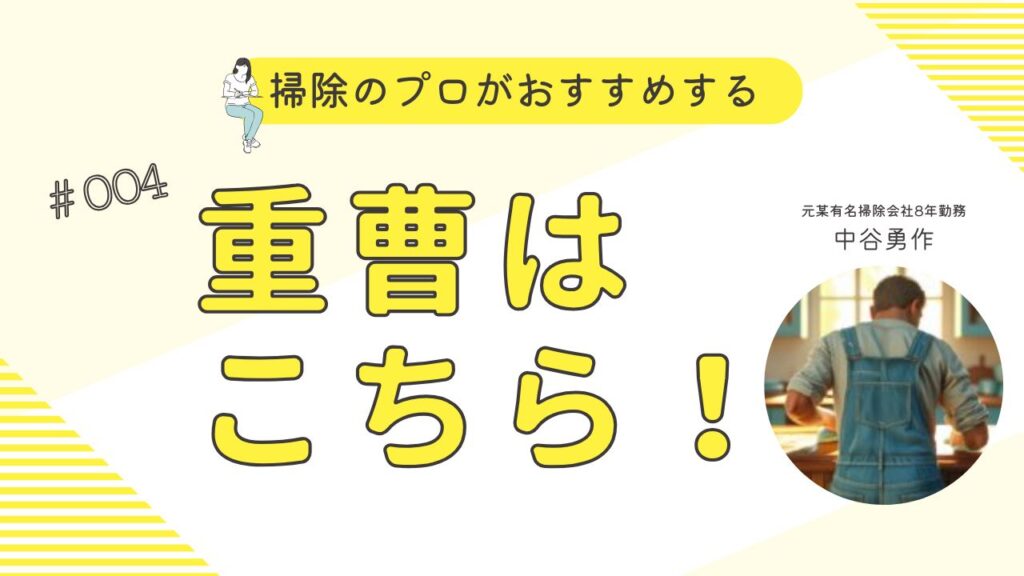
掃除の万能アイテムとして知られる重曹ですが、種類や用途に合わせて選ぶことで、より効果的に活用できます。ここでは、掃除のプロが実際におすすめする重曹を厳選してご紹介します。
重曹
重曹スプレー
重曹×クエン酸で汚れを完全攻略

重曹はアルカリ性の汚れを落とすのが苦手です。そこで登場するのが、酸性のクエン酸です。水垢や石鹸カスといったアルカリ性の汚れには、クエン酸が効果を発揮します。
重曹とクエン酸を組み合わせることで、ほとんどの家庭の汚れを安全かつ効率的に落とすことができます。
まとめ
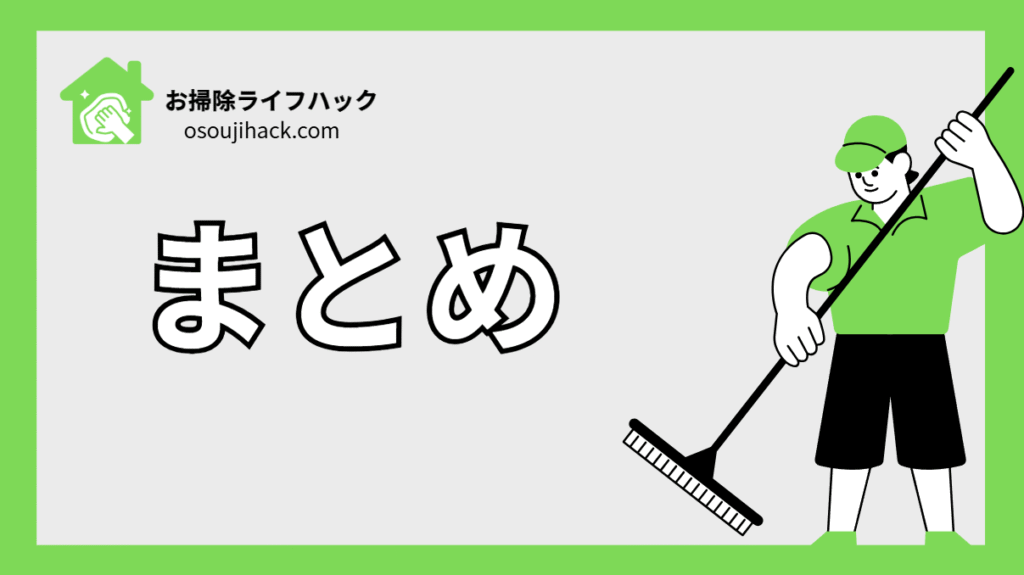
重曹は、ただの白い粉ではありません。その優れた中和、研磨、乳化、そして消臭作用は、私たちの生活を安全かつ環境に優しくきれいにするための強力な味方です。この記事で紹介した知識とテクニックを参考に、家中のあらゆる場所の汚れを撃退し、快適な毎日を手に入れてください。
化学洗剤の使用を減らすことで、地球にも、そして私たちの体にも優しいエコな暮らしが実現できます。ぜひ、今日から重曹を掃除のパートナーに迎え入れてみませんか?